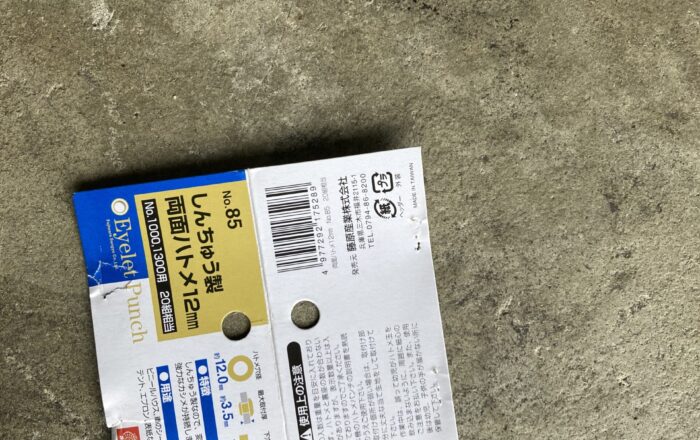10年近く前に部品取車の保管用にDIYで作り上げた畑の格安単管パイプ車庫。破風と呼べる程でもない只の妻側の三角の覆い。経年劣化でボロボロになってから早や幾年月。材料は買ってあったのだがモチベーションが上がらずにいた。香港の高層ビル火災を見てから怖くなり、根雪になる前に漸く着手できた。あとは所どころ穴が空いている隣の大工さんから貰った屋根のエンビ波板。来春以降、また作業に入らねば。
フロントワイパー
この冬にウインドーガラスを交換する羽目になってしまった元凶のワイパーの不具合。線状降水帯予報が出ている雨の日に乗ったら再発。と言うか夏まではどうにかこうにか端っこで止まっていたのだが、秋の長雨の最中にワイパーを動かし続けていたら突然ガラスの上端で止まるようになってしまった。冬の時は作業中にガラスが割れたので慌てて中途半端に応急修理で済ませていたのだった。
ワイパーモーターのストッパーとリンク板のシンクロが壊れてしまって、冬の当初の状態になってしまったのだ。シンクロ異常だけでモーター自体は機能しているのでモーターの本体は大丈夫と信じよう。締め付けナットが緩んだかリンク板側のノッチが削れてしまったようだ。
という事で整備日和の晴れた日に作業。ガラスが割れないよう慎重にボンネットとフロントデッキを外す。
アンサーバック
私の300Tdiレンジは93(KA)ガソリンレンジに98(WA)ディスコの300Tdiエンジンを載せているので必然的に純正のアラームECUと2ボタンリモコンを使っている。この10ASと呼ばれる緑色のECUはアンサーバック機能はついていない様だ。確か本国仕様の200Tdiレンジ(1ボタン)は93年型ながら純正仕様でアンサーバック機能がついていたはずだが、ディスコ乗りの友人に聞いてもこのECUはアンサーバックに対応していないらしい。設計者はロック・アンロックの2ボタンリモコンなので見ればわかると考えたか、あるいはディスコは車格がCRRより下なので省略したのだろうか。
近所のミニバン所有者はいつもピッピッとリモコンで施錠解錠をしていて煩わしい事この上ないし、更に最近の車は流行りでキュンキュンと鳴るハリウッドホーンというのもあるようだ。音はどうでもよいのだがボタンを押しただけでは本当に鍵がかかっているのか不安になることもある。先日などはキーホルダーを落としたらリモコン内部のバッテリーケースのハンダが外れてリモコンが効かなくなっていた。何回やっても施錠できないので電池が無くなったかと思ってバラしてやっとで分かった次第。別の日には雨が強くてドアロックのガチャガチャ言う音も聞こえないので走って行ってドアを開けようとしたら開いていなくて面食らった事もある。
という事で終活を兼ねてジャンクボックスにあったリレーやダイオードそれに単車用の格安フラッシャーユニットを使い(金を使わない様)アンサーバック機能を考えてみた。同じくジャンクボックスにあった壊れた純正リレーを解体して土台にして、小型汎用リレー2個とフラッシャユニットを継ないだだけ。
KA(93)レンジは盗難等異常時にハザード点滅やドアが自動的にロックされる仕組み(日本仕様には無いが)なので、ECU近くのリレーベースやコネクタまでは配線が来ている。これを利用してアンサーバック装置を付けてみた。車体側リレーベースの85(黒桃色)の線を直接アース、(茶桃色の)86の線を切断してブザーに継なぐ様に工夫して完了。
リアアッパーゲート
CRRのリアアッパーゲートはよく錆びる。天気の良い時しか、それも年に数回しか乗らない人はいざ知らず、普段使いしていると本当によく錆びる。考えてみれば当然のことで、屋根に降った雨や雪は後ろに流れ、アッパーゲートのガラスを伝ってアンダーゲートとクッションゴムの辺りで溜まりそこで乾燥するまで滞っているわけだ。 リテーナーというらしいがクッションゴムを取り付ける部分、これは幅2センチ弱で薄い鉄板をCチャンネル様にしてカーテンレールみたいにゴムを挟んで固定している。この部分がサビて朽ちているのでゴムが浮いて、更に雨水を呼び込みどんどん錆びていくという構造だ。常に鉄と水の接触で錆びない理由はない。200Tdiレンジの時も入手時から相当酷かったので新品同様な部品取車の物に交換したが数年で錆びた。その後アルミ製のリアゲートを輸入して自分で交換してようやく落ち着いていた。この社外品は全てアルミ製でリテーナーもアルミであった。
200Tdiレンジ譲渡の際、布製シートとアルミのリアゲートに若干未練があって交換のうえ譲渡しようかとも一瞬考えたが、深く考える暇も無く決まってしまったので実現できずにいた。
ただ、アルミ製のリアゲートは社外品しか存在せず、ハイマウントブレーキランプが付かないし曇り止めヒーターの模様も純正と違う、更に取り付け時に結構な加工が必要なので躊躇する人がいるのも事実。何より入手した時は送料込みでも10万円足らずだったがここ数年で20万円近くに跳ね上がってしまっているようだ。今となっては清貧の年金生活者には厳しい。
300Tdiレンジにして2回目の車検を受けて、改めてリアゲートを見てみたらやっぱりサビは進行している。という事で前置きが長くなったがリアアッパーゲートのアルミ化についての考察。
ガラスを嵌めるフレームはセットでしかパーツナンバーが付いていないがよく観察するとフレームの上辺は溶接だが下辺は分解できそうだ。錆びるのは理論的には台形ガラスの底辺だけのはず。このうち底辺はL型の鋳物をM5のネジで固定してある。つまり交換前提で底辺を鉄製で作ってあるのだがこれを錆びないアルマイト製などにすればよい。従ってL型鋳物が入って固定が出来るアルミチャンネルを探し出せばよい。そう考えてL=1,400で25✖️15ミリの黒塗装のアルミチャンネルと化粧用のW=40の平板をホームセンターで探し出し、加工して取り付けたのは10年ほど昔。その時はアルミリテーナーが見つからずそのまま放ってあったのだ。その後、◯ノタロウでリテーナーに使えそうなアルミのCチャンネルを見つけて300Tdiのリアゲートは基本鉄製だがアルミのリテーナー付きになっている。10年近くの時を経て行った二つの作業を合体させれば底辺がアルミ製でサビの来ないリアゲートは完成するということ。これで予備のリアアッパーゲートが出来上がりお金の心配なく老後を送る事ができる。
終の車を考える(細工こまごま)
巷では「終の車」論議が盛んだ。ポルシェに始まってジャガーやベンツ、ロータスやフェラーリ等々。「終」と言うより一度は乗ってみたい車あるいは自分の乗った一番の車あるいは車歴自慢という事なのだろうか。そしてそれを手に入れたり死ぬまでに一度は乗ってみたい、コレクションしたいという方やただの思い出話しの投稿が多いような気がする。
移動手段は車しかない田舎暮らしでは「終の車」というと運転免許証返納まで乗れる車と考える。財布に負担が少なく普段使い出来て何より自分の気に入った車、それを免許返納まで出来る限り長い間、乗りこなす事ができる車、これを私は「終の車」と考える。
若い頃はコロコロ変わる流行のデザインと性能を見比べて乗り換えてきたのだが、買い替えに倦んだ40代の頃にCCV(Cross Country Vehicle)誌(主宰:石川雄一氏)を読んで正に究極の車、終わりの車に出会った。以来四半世紀に渡ってCRR(Clasic Range Rover)を乗り継いできた。200Tdiディーゼル、V8ガソリンそして自分でエンジンを載せ替えて作り上げた300Tdiディーゼル。私はこれを「終の車」としよう。

⒈日課になった医者通いにも使えるサイズ感(カローラクラスの車長と車幅)
⒉徘徊で道路を外れてもどこからでも戻って来られる常時四輪駆動(4WD)
⒊お尻の肉が薄くなっても体に優しい絨毯のような足回りと座席
⒋手指が震えていても真っ直ぐ走れる操縦装置(ハンドルの遊び)
⒌耳が遠くてエンジン音の強弱が分からなくなっても目で解るタコメーター
⒍坂道発進や咄嗟の機転が効かなくても安心の自動変速機(4速AT)
⒎腰が曲がったり身長が縮んでも前が見える運転席(コマンドポジション)
⒏暴走老人にならないための自動速度一定装置(オートクルーズ)
⒐高齢ユーザー必須の下手クソ棒(代わりのボンネットタワー)
⒑霞んだ目にも足元を明るく照らしてくれるカーテシライト
11.弱ってきた足で踏んでも確実に止めてくれる電気アシストブレーキ(ABSも)
12.年金生活でも維持できる単価の安い燃料のエンジン(ディーゼル)
13.ヨレヨレで足が上がらなくても乗り込める踏み台(オートステップ)
14.消し忘れがなく安心してトンネルに突っ込める自動消灯装置(オートライト)
15.老人性視野狭窄でも後ろが見える後方鏡(デジタルインナーミラー)
16.パニックになっても状況を覚えてくれているドライブレコーダー
17.カンに頼らなくても電子系の故障箇所を教えてくれるOBD(On Board Diagnostics)
基本的にCRRは何も足さない何も引かないで完成された車のはずだが、製造終了後30年の時を経た今では技術的に進化した部分や陳腐化し不要な物も出てきている。これらを鑑みて細部を自分の気にいるように改良しながら免許返納まで乗っていくとしよう。
ドアを開けた時に点く足元灯とドアが開いていることを後続車に知らせる赤い警告灯。パドルランプとかウエルカムランプ、それに赤いのはドアランプとかエッジランプと言うそうだ。100インチベースのレンジローバーは基本はフロントドアにしか付いていないが後ろドアでも開いていることを後続車に知らせる赤い警告灯などは安全面から重要だと考える。
終活の一環で部品取車(LWB)の後ドアを処分しようと見回していたらランプが2個付いている事に気がついた。LseやLWB(Long Wheel Base)とかバンプラ(banden plus)と呼ばれる胴長レンジはいわゆるリムジン(サルーン)なので後席に乗るお客様をより安全に守るという考えのようだ。
滅多に後席に人を乗せる事のない300Tdiレンジだが、冬の間はスキー以外はヒマなので細々とした細工をしてみる。と言うことでお金をかけずにランドローバー純正品で300Tdiレンジの後ドアにランプを付けて見た(24.01の作業)。
夜間照明
ずーっと前にメーター周りやヒーターパネル辺りの夜間照明をLED化したのだが、実際にトンネルや夜間に走ってみると操作レバーの位置がどこにあるのか見えない。どうも元々のレバーに照明がないので周りが明るくなりすぎて見えなくなったようだ。鉄道模型用の極細LED照明が格安だったので工夫して取り付けた。
終活の一巻
根っからの田舎者なので物が捨てられない。ほぼ理想型で終の車のつもりの300Tdiレンジなのだが、暇ができるとまだまだやる事があるような気がする。
有効活用を図る上では純正品を使うMAレンジとWAディスコをバラしたので中古ながら純正パーツが結構ある。
オートステップは出来上がったのだが、いざ使ってみると運転席側はいらない気がしてきた。メインスイッチをつける事した。床下に放りっぱなしのリレーを固定するついでにシート下にある不要な燃料ポンプのイナーシャースイッチ(ディーゼルは機械式)を取り去り、キルスイッチの空いた穴に純正のスイッチを取り付けてみる。
車検整備2025
フロントガラスの割れに対応している間に継続車検が途切れた。とは言っても仮ナンバーで持ち込んで受検できるのだが、2ヶ月ほど空白期間ができた。その間、若干暖かくなってきたので前から気になっていたリアブレーキディスクを新調し、ブレーキフルードのエア抜きをしたうえで検査に向かった。ヘッドライトは左目の内側に水滴が付いていたので拭いてから向かったのだが案の定やっぱりバツが出た。こんな事もあろうかとコイト製のライトを持参していて正解だった。交換のうえ検査場近くの整備工場で調整して貰ってようやくマルが点いた。

フロントガラス
300Tdiレンジのフロントガラスが割れた。自分の不手際で割ってしまった。ワイパーモーター修理の際、ボンネットヒンジのバネに弾かれたコジリ棒がガラスに当たって割れたのだ。

元々こういう時のためにズーっっと前に椅子無しの部品取車を購入しパーツは綺麗にむしり取って保管してあるのだが、部品取車は左ハンドルの後期バンプラ仕様だったので合わないものや不要なものは売却して生活の足しにしていた。フロントガラスは前期型とは違うことはわかっていたが、こちらは売却は大変なので畑の車庫に放ってあった。KA(93年型)まではゴムシールを車体に嵌め込んだ上でガラスを嵌め込む方式だしMA(95年型)後期はガラスを車体に直接貼付る方式で縁のゴムは本当のモール、唯の飾りである事は知っていた。
ただここに来てまさか本当にフロントガラスが必要になるとは思いもよらなかった。赤貧の年金生活者には純正新品パーツの熱線入り前期型ガラスの数十万円はするであろう出費は痛い。そもそも入手経路さえネットでは見当たらない。交換の記事も見当たらない。やはりプロの世界の話なのだろうか。
せっかく今までDIYにこだわってきたので、いい機会だ手持ちの後期型が前期型に流用可能か真剣に考えてみよう。畑の車庫の整理の意味も含めて後期型純正ガラスが前期型ゴムシールに使えるか検討してみた。
割れの入った前期ガラスの寸法と後期型のガラスの寸法はおおよそ同じように見える。パーツリストの品番は当然ながら違うがガラス自体のサイズは前期、後期とも同じと信じよう。違いは後期型が縁取りが黒くなっている事。熱線入りの純正品であることは同じ。コネクタの違いなどは瑣末な事。せっかく持っている物を使わない手はない。
いざ友人に手伝って貰うべく電話しようとした日の朝、信頼できる情報筋(SNSだが)でディスコ1(0では無い)のガラスをレンジの物に交換した投稿があった。その情報ではディスコの貼り付けガラスの方が若干だが短いとのこと。糊つけ部分があるので貼り付けガラスの方が長くなると思い込んでいたが逆らしい。
慌てて再度精細に測ってみると高さは同じだが部品取車の貼付式ガラスの方が上と下(長辺)が2センチほど短い。困った、情報によると嵌込式ガラスを後期型ボディには取り付けできるが逆は不可とのこと。その通りだったのだ。裏技的にガラスや内装を全部外してAピラーに鉄板を溶接するか、イヤイヤ下辺はハードダッシュの受けも兼ねているので貼り付けは困難なのだ。完全にアウトだ。
こうなったら最後、LR仲間の大先輩にすがるしかない。星の数ほどある膨大なコレクションから前期物のガラスと手持ちの後期型とを交換して貰うしかない。無理やり頼み込んで遥々神奈川県まで取りに行ける事になった。純正オリジナルとDIYにこだわってきた者としては(中古だが)純正トリプレックスのガラスで揃えられるのが嬉しい。

実はこの話は「割れのないガラスをすんなりとDIYで交換しておしまい」とは行かなかった。2月中旬の大雪の日に神奈川県で貼り付け式ガラスと嵌め込み式ガラスを交換して貰ってその1週間後に助っ人と二人で意気揚々と嵌め込もうとしたところ取り付け手順を誤り、最後の最後でパリンと2つに割れてしまった。またまたやってしまったのだ。
その後、大先輩の大御所に平身低頭頓首再拝して、車体から自分で取り外し不用心なので割れたガラスをその部品取車に取り付けることを条件に再度某隠れ家に通う事になった。最初に割ってしまってから2ヶ月近くが経過し、300tdiレンジは車検が切れてしまったので、サンバーTT2で高速や首都高を走ってようやくにして取り付けることができた。
今度は慎重に車庫内で一人で時間をかけて取り付けた。とは言っても半日で完了したが。
サンバーにオートライト
ズー〜っと前からサンバーにもオートライトを付けられたらとは思っていた。ディーラーからライトまわりの回路図を貰ってきたり、ネットの情報は集めてはいた。情報によるとスモールとヘッドライトはそれぞれプラスコントロールとマイナスコントロール。ただ、スイッチ部分は一体型のコラム(ハンドル)スイッチの中にありコネクタから出ている信号は単純にアースピンとハイ・ロー切り替え信号ピンだけのようだ。つまりステアリングを外したうえでハンドルコラムを取り外さなければスイッチ部分の詳細は見えないらしいという事で躊躇していた。

そう言えばライティングスイッチユニットがジャンク棚にあったはず。数年前に友人のサンバーを格安で買ったもののキーを紛失してしまったので中古のハンドルコラム一式を入手して純正リモコン付きにして、その上で売り払って小銭を稼いだのだった。レンジの作業が行き詰まって暇な時にこのライティングスイッチをじっくりと観察して、マイナスコントロールのスイッチ部分を探し出しオートライトキットを作ってみよう。リレーと光センサーは確か余った物がどこかにあったはず。

最近は中華製であるが種々様々な汎用ユニットが格安で売りに出ている。3個千円とか1個400円とかで調整可能な光制御スイッチとか遅延タイマーがあるのだ。自作が調子悪ければ工夫してこれらを2個繋げればよいだけだと気がついた。つまりどうあっても1組千円足らずで出来上がるわけだ。純正風にこだわる者としてはいかに違和感なくセンサーやスイッチを取り付けるか、こちらに力を注ぐ。

今年(R7年)の雪
青森や新潟ほどではないようだが、今年はいつになく雪が多い。
ワイパーモーター
雪のせいでワイパーが壊れた。というか壊してしまった。冬の初めに車庫に入れずに外に駐車していて一晩で30センチほど積もった事があった。横着してウインドガラスに溜まった雪を無理やりワイパーで除雪したら雪の重さに負けてワイパーが擦れてしまったようだ。その後ワイパーを動かす度に所定の位置に収まらず徐々に途中で終わるようになった。ひと月ほど経ってからワイパーアームの取り付けを調整したが最後はワイパーが全く動かなくなってしまった。ヒューズが飛んだかとも思ったがウオッシャー液は出るのでモーター自体が壊れたかアームとモーターのギザギザ(ノッチ)が削れてしまったかどっちかだ。モーター自体は結構丈夫なはずなのでノッチが削れたと見込んでモーターを観察して見た。
CRR(Classic Range Rover)の場合ワイパーモーターに辿り着くのは骨が折れる。クソ重たいボンネットを外し更にデッキパネルを外さなければならないのだ。バネが強すぎるボンネットヒンジを水平にしてデッキパネルを外そうとしてコジリ棒を入れていたら手が滑ってバチンとどこかに当たって飛んで行ってしまった。取り敢えずパネルを外してモーターを観察したが、後でどこに当たったかしっかり見てみたらフロントガラスに当たってから飛んでいったようだ。イタタタ。φ3センチほどがヒビ割れ隣に約10センチ径で丸くヒビが入っている。本当にイタタタタだ。下手なことをした。ワイパーの修理どころではなくなってしまった。
ジャンク品棚にエンジンドナーとなったディスコのワイパーアームがあったかと探したが左ハンドルのMAレンジの物しか見当たらなかった。ディスコのボディを売り急いだためワイパーアームを取り外し忘れたようだ。今となっては自分自身の軽率さを呪うしかない。所謂前期型のKAと後期型のMAではモーターの芯径やコネクタの形状も違うようだったので取り敢えず現在のモーターの取り付けノッチを清掃してキツく締めてお終い。次の大仕事のウインドガラス交換に備える。